
本日、長岡市関原の馬高縄文館で、昨日雨で繰延になった野焼きが行われました。
馬高遺跡出土 火焔型土器A式2【原寸】

さて、本日わたくしが焼いてもらった土器はこれ↑
昨年秋から悪戦苦闘してた火焔型A式2。
鶏頭冠(土器上部にある四つの飾り)の向きが、有名な馬高「火焔土器」とは逆なのです。
-

火焔型A式2 鶏頭冠が右を向いてます -

「火焔土器」鶏頭冠は左向き
自身初の原寸の土器で大きく感じてしまうわ、

ちょいと歪んだオリジナルをどこまで再現するのか…
できるのか?!
全体のバランスをとるのが妙に難しくて…なかなか苦戦。
昨秋作り始めてから年を超えてなんとか完成させて乾燥させていたものを、
本日やっと焼くことができました。
野焼き
まずはウォーミングアップ的焚火

朝の9時に会場に行くとすでに土器が並べられ、焚火が始まっていました。
持参した土器を一緒に並べます。
温度差がありすぎると土器が割れてしまうので、まずは焚火の周りで温めます。
と同時に、地面の水分を蒸発させるための焚火です。
これが1時間から1時間半ぐらい。(温度や気象条件で変わってきます)

土器を焚火の中に移動

火がいったん落ちるのを待って(実際にはまだ消えていませんが…)
焚火中央部に温まった土器を移動させていきます。
灰をどかして平らにして、そこに土器を並べていきます。
壊さぬように~丁寧な作業。
写真では伝わらないけれど暑いんですよ。いや、「熱い」か。

再び薪を積んで着火!

土器を並べ終えたら再び周囲に薪を積んで着火します。

いよいよ土器焼きって感じがしてきました。
土器の温度が上がります。

炎で煤けてきました。
煤をかぶらないとキレイに焼け切らない可能性もあり、ここでは真っ黒になるのが理想なのです。
ひたすら燃やし続ける
さて、ここから1時間ほど燃やし続けます。
縄文館の方は火の番で薪をくべ続け、その間参加者はお昼を食べたり、縄文館を見学したり。

私も縄文館の中でお昼をいただいてちょっと休憩。
遠巻きに火を眺めながらひとときぼーーーーっとさせてもらい…
なんだか贅沢な時間の流れを感じます。

いよいよクライマックスへ!

午後1時頃。
いい感じに土器が煤けています。
ここからいよいよクライマックスです。

薪を一気にくべて、炎をmaxにーーー!!
ごおおおおおお。
むやみに近づいたらいけません!
ややもするとメガネが解けたり、スマホが熱で強制終了します!
この時の温度は600度から800度くらいになります。
焼き上がった土器が姿を現すわす時のドキドキ~
一気に火が入った後は、自然に落ちていくのを待ちます。

薪が灰になってどんどん小さくなっていくと、白くなった灰の中から真っ赤に焼けた土器が姿を見せます。

ドキドキ土器。。。
あーーーーーーーーーーーーー!!!

鶏頭冠が一個落ちてる………!!!( ;∀;)
いやあ、まあまあ、あることです。
仕方なし…(´ノω;`)
これもまた、野焼き本来の味わいでもありましょう…(強がりか!)
焼き上がりはそれぞれ~
火が落ちたら焚火の中から土器を出します。
まだまだ土器は熱いので素手では持てません。
持ち手の長いやっとこでつかんで出してもらいます。

冷まし中の土器はなんだか発掘したみたいですね。
落ちた鶏頭冠は、さいわい丸ごと無傷(?)で焼き上がっていましたので修復は可能。
もう一か所の鶏頭冠はぎざぎざの鋸歯状突起が三つほどとんでしまっていて、
こっちの方は細かく割れたみたいで見当たりません。
焚火の中に壊れた破片がないか探してもらいましたが、まだ焚火の中は熱々なので…
後日ラッキーだったら見つかることでしょう。
私の土器が一部壊れてしまいましたが、全体的にはみなよく焼けています。
イベントでつくった土器さんたちも、みんなきれいに焼けていましたよ。
お疲れさまでした!
土器が冷めて手で持てるようになったら終了です。
皆さん自分の土器を大切に抱え、帰宅の途に就きました。

馬高縄文館の皆様、本日は大変お世話になりました。
ありがとうございました!
実は小物の二度焼きも

帰宅して改めて見るA式2。
落ちた鶏頭冠がなんだかオブジェのようで、これはこれで飾ってもいいかもしれないなんて思ったり。
さて、実は小物も一緒に焼いてもらいました。
去年作って野焼きしたのだけど煤が残ってたので、今日二度焼きして煤を飛ばしたのです。
ミニミニ火焔ちゃんと猫耳型謎の植木鉢。


こちらは素晴らしい出来!
猫耳植木鉢もいい感じなので、これには何か植えたいと思います~♪
秋の良い一日…。ありがとうございました。
今日も感謝と共に♪
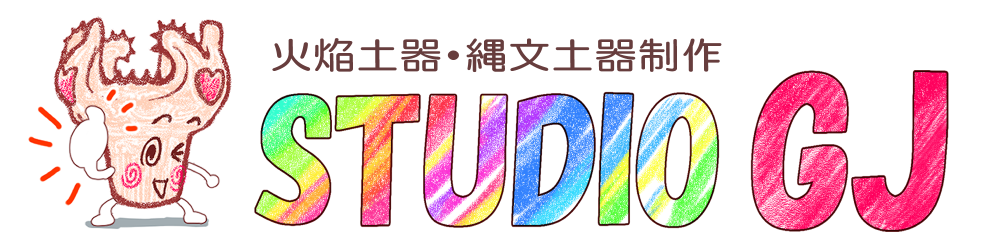





コメント